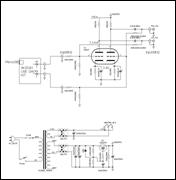���y�f�[�^�����L���悤 |
![]()
|
���_ ���쒇�Ԃ�JN1NDK�ǂ���A���{�l��HP�ŏЉ��Ă���BanaPi���g����MUSIC�T�[�o�����B ���R�́uBananaPi STD�v�ł́uI2S�C���^�[�t�F�[�X�v���T�|�[�g���Ă��Ȃ��ׁuBananaPi_Pro�v�ł������ꂽ�����ŁA�����ŗL���Ɋ��p�����Ē������ɂȂ����B STD�łƂ͂����A����RSPi���y���ɍ��X�y�b�N�ŁA����USTA�[�q���L��̂́A���ɂ��肪�����B ���������̂�CPU���OS�C���X�g�[���ς݂�SD�J�[�h�A�A�_�v�^�A�P�[�X�ꎮ�ł���B �����USTA��2.5�C���`500GB��HDD�����t���āA�ƒ��LAN�ڑ���NAS�Ƃ��ĉ��y�₻��ȊO�̃f�[�^�ۊǂ��\�ƂȂ����B �yDAC�z DAC�́A�ȑO�ɓ��肵���H���d�q��PCM2704�@DAC-KIT���g�p�����B �yBufferAMP�@�z DAC�o�͂̃o�b�t�@�A���v�́A2SK-170�̍쓮�A���v���쐬�B �e�X�^�[��2SK-170��IDss��I�ʂ����y�A����荷���A���v�Ɏd�グ���B 2SK30���e�X�^��IDss���͂���AL-Ch�ARch�̒�d���l���o���邾�������ɂȂ�悤�ɂ����B �o���b�N��Ԃœ���m�F�����Ƃ���A�m�C�Y�������Q�C�������x�ǂ������B �yBufferAMP�A�z ���̌�A��͂苅�ɍS�肽���Ȃ�莝����12AU7�̍����A���v�������Ă݂��B �������A�g�p�����g�����X�̗e�ʕs���ƁA���ꃁ�[�J���̃`���[�u���Ȃ������̂� ������1�{�ő����PG�A�҂œZ�߂��B Gain�͂��悻200K��68K=2.9�{ �y�g���z ������A�V���ȕ��i�͍w�������A���荇�킹�̕��i�ō�邱�ƂƂ����B �d���g�����X�́A�u���E���ǎd�l�̑���킩��O����JUNK�i�ł���B �ꎟ�^�b�v��2�n���A����2�n���o�͂���Ă��邪�A�q�[�^�p6.3V��1�n���̂݁B �����A����AMP�ɂ��ׂ�12AU7��2�{�_�������Ƃ���5V�t�߂܂Ńh���b�v�_�E�����Ă��܂��A�O�̒��̗e�ʂ͎��Ȃ��B �{B�d����180V���Z���^�[�t����2�n���o�͂���Ă���B �u���b�W�����{�����b�v��������H�Œ��x250V�o�͂��Ă���B �����̓d���R���f���T�́A�f�W�J���̃X�g���{���j�b�g����O�����`���[�W�p��80uF/300V�ψ��̕����������t���Ă݂��B �e�X�g�i�K�Ńn�������C�ɂȂ�A�q�[�^�d���������_�Ƃ��A���b�v�������ɃR���f���T�𑝂₵�Ă݂����A �p���[�A���v���ő�ɂ������ɁA�������ɕ�������n���������S�Ɏ���Ȃ������B �����͋��炭�g�����X����̉�荞�݂̂悤�ł���B �V�[���h�t���\�P�b�g�Ɍ�������Ηǂ��̂����A�\�P�b�g�����͖ʓ|�Ȃ̂ŁA���̂܂ܑg��ł��܂��B �P�[�X���ė��p�i�Ńg�����X�̍����ƒ��x�����[���ł������B �����ɁA�g�����X�A12AU7�AAKI_DAC������t�����B ������BananaPi_MPD�Ɠ������Ȃ̂ŏd�˂���T�C�Y�ł���B �t�����g�p�l���ɊJ���������݂��Ƃ��Ȃ��̂ŁA������ڂ�B���ɉ����܂݂�t���悤�Ǝv���B �g�����X�J�o�[�������A�����ɂP���^�b�v������ɏo�Ă���̂ŁA���ɐ≏�e�[�v�ŕی삵�Ă��邾���Ȃ̂ŁA�ނ��o���̃g�����X�^�b�v�Ƌ��ɂ����ꉽ�Ƃ��������B �y���z�z �o�̓Q�C���̓p���[�A���v�����S�h���C�u�ł���悤�ɂȂ�A�X�� ��悪�啝�ɐL�т��悤�Ɋ�����B���܂����x�[�X���͕����Ă��Ĕ��ɐS�n�����B ������RS-Pi�ł́AUSB-HDD���q���ł݂���NAS�Ƃ��Ă̎g�p�͎��p�ɑς��������x���������� BananaPi�ł́A�S���X�g���X�����������Ȃ��B PC����l�b�g���[�N�o�R�ʼn��y�t�@�C���𑗐M���Ă��A�ʏ�̃l�b�g���[�NPC��NAS�Ԃ̃f�[�^�]���ƑS���ς�Ȃ��B ��������Ɉ���x���Ă���B �Q��URL: http://www.op316.com/tubes/pre/tc-pre.htm http://www.n-mmra.net/audio/dac2/dac2.html http://neax.sakura.ne.jp/tube/amp/amp2/
|